~DIYで雨漏りを修繕したが原因は1箇所だけではなかった/窓上の雨漏りは複数の水の道から流れてくるのでシャワーテストが重要~
ある日、和室の高窓の枠の上部から雨漏りしてきて、障子紙がビショビショ。
木のアクを含んだ水で障子紙が茶色いシミだらけになっていました。

雨漏りって屋根からだけじゃないの?

窓枠の上は水が真下に逃げて行けないから、サッシ屋さんは防水シートの順番を考えて、念入りに防水するくらい頻度があるんだよ。
自分で雨漏りの原因調べ
ネットで調べると、雨漏りの原因は複数あることが多く、素人が見つけることは出来ないという記事が出ていました。
しかし、いつもの癖で、私が原因を探してみて、自分で出来そうならDIYで施工してみようと、またまた思ってしまったのです。


分かりにくいですが水染みがたくさん付いてます。
ネット記事が言うとおり、雨漏りの原因は表面から見ただけでは、わかりません。

もしかして、屋根付近の破風あたりから雨水が入って、内壁の防水シートをつたっているのかなぁ?
だとしたらDIYでは無理だ…。
でも自分で出来ることはやっておきたい!
とりあえず外から見て、1階と2階の間にある帯板に付いている水切り(我が家の帯板には珍しく水切りが付いている)に対してテストしてみよう…。
帯板の水切りは、家の角に行くと、折れ曲がりになり、継ぎ目状になっています。
そこにコーキングを施して様子を見ることにしました。
これは、雨漏りしている箇所から離れたところが原因であることが多いという記事を読んだからです。
何日か経ってまた雨が降りました。
ダメでした…。
同じ箇所から雨漏りしています。
そこで発想を変えて、水が出てくる箇所から、水の気持ちになって逆の道を想像してみたんです。
そして思いついたのは、この戸袋のマウントの部分。

(この画像は施工後)
雨戸の戸袋のマウントは、外壁側から中に差し込んだ形状だったので、早速、この部品の壁まわりのモルタルをカッターで切除して深部を覗いてみたんです。
すると、壁の中のモルタルがグチャっとしています。
雨漏りの原因を発見しました!
DIYで雨漏り修繕
ビンゴ!ということで、ドライヤーと夏場の外気で内部を乾燥させ、私がDIYでよく使う変性シリコンを注入しました。
塗料は、家の外装塗装をやった時のものをストックしてあったので、これを使います。
変性シリコンなら、塗装はOKです。
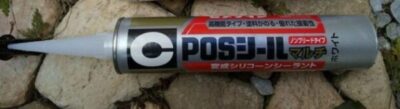

壁との接合部をくりぬいてシリコン充填。
壁柄も作りました。
水色の部分です。
分からないでしょ?イイ仕上がりです。
これで完了と私は満足していました…。
また違うところから雨漏り発生!
ところが、別の日の台風の横風の吹込みが強かった日のこと。
雨が止んで1時間くらい経ったら、同じ高窓のサッシ右側上部からポタポタ。
これまでとは違う箇所です。
私のプライドは崩壊しました。(大袈裟ですけど、それくらいガックリしました。)

2箇所目の原因探し
チクショ~ということで、外壁に素人の見よう見まねでシャワーテストをしてみました。
雨漏りするまでに時間がかかるので、どこにシャワーした時に雨漏りするのかが、せっかちで作業経験のない私にはハッキリ判断できませんでした。
何日か経って横風と雨の強い日、しばらくするとやっぱり障子紙が濡れ始めます。
この状況から、横方向に水が入ってくる事までは察しがつきました。
そうすると、やっぱり1階と2階の間の帯板(幕板)部分が怪しい。
他に開口部がないことから、ここから入っているという仮説を立てました。
我が家の帯板には、水切りが付いていることは前述しましたが、水切りの奥にはどうも雨返しが付いているようなのです。
棒を突っ込むと横に向かって全体的に当たる物があるからです。
細い隙間で奥の方なので、LEDの強い光をあてても見えません。
応急処置の結果で水の侵入箇所を特定したい
きっとこの構造は、2階から内壁に水が入った場合の水抜きである可能性がある。
また、家の周りは同じ構造なのに雨漏りしないのは、雨返しがあるから水が入らないのでは?
そう考えたことが、私のその後の判断を鈍らせました。
自分で帯板の隙間を閉塞することには躊躇してしまったのです。
テストとして隙間全部に細長く切ったスポンジを詰め込んでみました。
スポンジの理由は、外からの侵入水はスポンジが吸収し、雨返しで堰止め。
内壁からの排水は、スポンジが飽和したら水切りを通って排水。
そう考えたのです。
そして、普通の雨では雨漏りはしませんでしたが、次の台風が来たらまた雨漏りしました。
テストの結果が予想と違います。
そうなると、雨返しがどこか欠損?しているということになります。
後に、これが正解だったことは、まだ気づいていませんでした
DIYの施工方法に迷いが…、プロの出番。
仕方なく、雨漏り診断士の認定を受けている最寄りの建築事業者に診てもらいました。
これまでの状況説明をし、帯板の開口部が怪しいとの仮説を伝えました。
職人さんからは、雨漏りの原因は、通常、複数あるはずで、1箇所は私がDIYで施工した箇所、その他の箇所は、帯板部分を中心に建築図面を見ながらのシャワーテストで判断しようということでした。
さて、診断開始です。
私は興味深々でした。
シャワーテストは、梯子にシャワーを取り付けて、10分くらい定点放射しています。
1時間程度空けて、漏れてこないかチェック。
出てこないので、梯子を横にずらして、また定点放射。
この作業を3回くらい繰り返したところ、意外な場所で漏れ始めました。
一旦、雨漏りが止まるまで放置して、その箇所に再度放水し、間違いないことを確認しました。

斜めに水の道が出来ていました。
雨水の侵入口は窓枠から45度斜めに2mも離れているところです。
ネット記事で斜めに水の道が出来ることがあるということを知っていましたが、再度、建築図面を見たところ、その場所には筋交いがあって、それをつたって窓サッシ上部に到達していることがわかりました。
水が入ってくる箇所は、帯板の開口部が他の箇所より細くなっていて、中が覗けないので、水切りの根元の雨返しが欠損しているのかは目視では確認できません。
しかし、この箇所だけ雨返しが欠損していることに間違いありません。
ちなみに、隣の家の大きな木を切ると横からの吹込みが起きて、こういう現象がよく起きるのだそうで、確かに隣の大きな木を切ったばかりだったのです。
初日の工程は、5時間かかりました。
大工さんの知識から工法を決定
職人さんの判断は、別の日の乾いた状態で、帯板と水切りの隙間に変成シリコンを充填したいということでした。
私が危惧していた2階からの水抜き機能のことを話すと、この状況からは帯板(幕板)の水切り機能を特に考える必要はなく、たとえそうであっても、窓枠上の一辺だけを塞ぐので、横から排水されて問題はないということでした。
また、先に私がDIYで施工した、もう1箇所の雨戸の戸袋のマウント部もチェックしてくれましたが、よく出来てると褒められて、うれしかったです。
それ以降、雨漏りはありません。
とても勉強になりました。
まとめ
雨漏りの原因は複数ある。
かなり離れた所からも筋交いなどをつたって斜めの水の道が出来る。
雨水の侵入口を塞いだつもりで、外への水の逃げ場を塞いでしまうことがあるので、入口を閉じるのにも建築の知識を要する場合がある。

雨漏り修繕って大変なんだね。

今回は私もプロの技を学んだよ。
高所作業になる場合はDIYでは無理だね。

