~温故知新とDIYの復興精神は未来に向けた期待で一致する/昔弾いていたギターに再チャレンジして覚醒と復活に向けた心のDIY~
私は、ギターを弾くたびに昔のことを思い出すのです。
今さら遅いという無念さも重なって、悪夢に出てくることもあります。
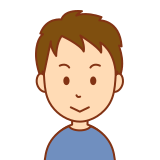
僕は、あー、あの時、あーしとけばもっと上手くなったのに!とか考えますけど、そういうことですか?

そうそう、あんな未熟な状態で、よく恥ずかしげもなく、人前で弾けたもんだよな~とか、悔いることばかりだよ…。
しかし、それも意外とまんざらではなくて、逆に「あーしたらこうなる…。こーしちゃいけない…。」という教訓にもなっているのです。
教訓とは、将来に向けて意義があるものですが、私も、ざっと人生の65%くらい使ってしまいました。
あとは35%しか残ってないようですが、温故知新で活かせるのなら、無念だったことも無駄ではなかったのではないかと思えるようになってきました。
ということで、今回は、私がギターを初めて触った頃の周囲の環境から話しをはじめます…。
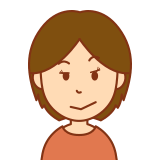
そんな話、聴く人なんかいないわよ…。
ギターに初めて触った頃の町の様子
子供のころの自宅の周辺地域の様子は、自宅を出てから坂を下りたところに県道があり、そこにあるバス停から15分おきに来るバスに乗り、10分ほど揺られていると、国鉄東海道線と横須賀線が停車する駅がありました。
駅前の商店街は、いつもたくさんの人が往来していて、専門店の佃煮の匂いや、おでんの具を専門に売っている店の前では、揚げ油の甘い香りが漂っていた。
私はそれが好きだった。
とりわけ印象に残っているのは、今でいうファミリーレストランの元祖ともいうべき不二家レストランが駅の西口正面にあって、店の入り口の横には、プリンやシュークリームを作っている製造ブースのような部屋があって、外からガラス越しに見えるようになっていた。
そこのガラスはいつも蒸気で曇っていた。
バニラエッセンスの香りがプンプン漂っていた。
水滴のついているガラスの向こうでは、白衣を着て白帽子を被った人が行ったり来たりしている。
おそらく、次々に仕上がる商品をオーブンから搬出したり、これから加熱する生地をオーブンに入れる作業に追われていたのだろう。
そこの場所の前には、タクシー乗り場があって、まだまだ交通が不便な当時は、昼間なのに多くの行列を作っていた。
この人たちは、なかなか来ないタクシーを待っているのだけれど、幼いころから「きっと不二家のケーキやプリンの匂いをずっと嗅いでいるのだから、幸せな気分なんだ。」と思い込んでいた。
だから、持ちくたびれて怒り出す人はいないんだろうと思い込んでいた。
私の住んでいた地域で栄えていたのは、その駅前商店街のみで、自動車で数分離れると高度経済成長期で急激に進んだ宅地造成ブームの不毛な光景が目の前に拡がっていた。
初めてギターに触った
さて、私が初めてギターに触った時の話に入ります。
そのギターは、駅の反対側の東口に小さなレコード店があって、クラシックギターやフォークギターが、レコード陳列用のワゴン棚の上側に8本位いつもぶら下っていたので、見るたびに「いいなぁ~、欲しいなぁ~。」と思っていたのです。

この頃は、ギターの種類や音色の違いなんて知らないから、そこにある物なら何でもよかったんだよね…。
記憶にはないが、エレキもぶら下っていたのかもしれない。
おそらくモズライト…。
ベンチャーズ、加山雄三、寺内タケシ…etcの時代、必ずあったと思う。
あの頃は、楽器専門店は横浜駅まで電車に乗って行かないと無かった。
だから郊外の地域では、レコード屋さんで楽器も販売していた。(今でも同じ?)
ちなみに私の住む横浜では、だいたいどこの駅でも東口は西口よりも静かな感じがある。
これは、横浜という地形上、港が全市域の東側にあって、住民は相対的に西側に住んでいることになるから、私が子供のころ住んでいた地域の最寄り駅も東口は物静かであった。
夕食の買い物などで賑わう西口との違いは、子供の私でも感じとっていた。
その東口にあったレコード店は、現在のような大企業のチェーン店とは違って、個人営業の小さな店。
それでもスピーカーを外に向けてガンガン音を出していたから、若者が自然と集まる場所だった。
今思えば、東口の振興の拠点だったかもしれない…。
私はその店で、弦が柔らかいという理由だけで、クラシックギターを買ってもらった。
9千円くらいだったと記憶している。

店内では、恥ずかしくてボロ~ンと音を出すことすらできなかった。
バスに揺られて家に持ち帰った頃は、もう夕方で、NHKの「みんなのうた」の時間だった。
見よう見まねで練習を始めたのが、「北風小僧の寒太郎」。
チューニングがしっかり出来ないのに、いきなりチャレンジしちゃったのだから、我ながら大したものだ。
小学校の残る5年生、6年生の2年間は、とうとう北風小僧の貫太郎しか弾けなかった。
メインに使うギターの変遷
中学校になると既にフォーク・ニューミュージックブーム。「コッキーポップ」「つま恋」というキーワードが、ラジオの深夜放送から毎日聞こえていた。
ニューミュージック時代、当然フォークギターが欲しくなった。
友達には既にエレキを上手に弾く者もいたが、その100%が兄貴の影響だった。
私の場合は、兄もおらず、公団の高層アパートに住んでいたから、音を外部に漏らすことがタブーだったので、エレキへの転向はハードルが高かった。

今思えば、生ギターの方が直に音が出るので、エレキでヘッドフォンを使った方が近所迷惑にはならなかったはずだよね。
これに気付いたのは、相当あとになってからのことだったな。(笑)
牛乳配達のアルバイトをしていたので、1万弱の小遣いは持っていたが、親に「軽音部でどうしても必要だから。」とねだって、Morrisのフォークギターをやっと買ってもらった。
1万5千円だったと思う。
中学生のころは、荒井由実、ハイファイセット、かぐや姫、風、アリス…etcのニューミュージックのレコードを持っているのが普通になっていた。
私は、この頃からステージの前方で歌っている人よりも、バックで演奏している人の方が気になり始めていた。
特に「風」のバックで弾いていた石川鷹彦の奏でるMartinギターの音色には衝撃を受けた。
有名な「22才の別れ」のイントロを弾いた人(上条恒彦の六文銭のギターだった人)である。
ギターの《音色》で衝撃を受けたのは、この時とラリーカールトンだけだ。
演歌歌手のように、出てくる音の響きに「情」がこもっている。
中学2年、エレキギターを弾きはじめた
《サウンド》のカッコよさを知ったのは、ジェフ・ベックを聴いた時。
アルバム「ワイヤード」でジェフ・ベックのトレードマークになっていた白いストラトが欲しかった。
バイト代やお年玉をコツコツためていたので、とうとう初めてのエレキギターを手に入れた。
そして、その他に印象に残っているのは、ライトハンド奏法を初めて見せつけられた、エドワード・バン・ヘイレン。
作曲やギターアレンジのセンスで言ったらリーリトナー。
当時は、フュージョンではなく、クロスオーバーと言っていた。
エレキギターを持つことは、みんなよりランクアップしたかのような感覚があったのを覚えている。。
18歳以降、もっと真面目にやってればよかった。
~18歳以降の記憶は、悪夢の中に断片的に出てくるのです。~
高校3年生の頃には、企画会社の斡旋で いくつかのバンドと共同で当時の30㎝LPに楽曲を収録してもらって販売したこともあった。
20歳の頃には、ハワイの音楽フェスティバルに出る機会があって、1週間滞在して、オアフ島の野球グランドに設置された2日間の野外ステージで、スタッフバンドで何曲か演奏したこともあった。
この頃、蒲田のダンスホールでブラス付きのバンドに1週間の契約でお誘いがった…。
耳の肥えた常連客が沢山いる店だというのを知らずに出たんですが 1日でクビ。
帰り際に年配の方から「やめちまえ」と言われたのが37年経ってもトラウマになって、人前で弾くのが嫌になったのです。
またこの頃、某大手のラジオ局でアルバイトしていて、そこのプロデューサーから、スタッフとしてやる気はあるかと聞かれました。
その時、好きな音楽ジャンルを聞かれて、何も考えずに素直に答えたら「そのジャンル以外を担当しないと成功しない、メディア業界はマニアでは聴視率を上げられない」と…。
結局別世界に就職しました。
社会人になってからは、会社のバンドに誘われて、社員の結婚式などでコミックバンド風なことは、時々やっていました。

この頃は、既に理解していなければいけないはずの演奏に取組む姿勢、感情の入れ方、音楽理論などが全く中途半端で、成長していく見込みは全然ありませんでしたね…。
以降、未熟と後悔の記憶しか残っておらず、トラウマ的になって、私は多くの人前では楽器を弾くことはなくなったのです。
ギターに対して、真面目に取り組むようになったのは、40代になってから。
この頃の自宅の隣駅には、いつも数人しか客が入っていないジャズ系のショットバーがあって、マスターに誘われて、決まった曜日に人前でギターを弾くようになっていました。
高3の時に同級生の兄貴から譲ってもらったジャパニーズビンテージのセミアコが、物置の奥に1本だけ埃を被って残っていたのを見つけた頃です。
これらがきっかけで、「このセミアコを何とか生き返らせて、出せる音色を最大限引き出したい。」という感情が、内面から湧き出たのです。
DIYのカテゴリーに、ギターメンテナンスが入っているのは、これが理由です。
今でもその感情は、ONの状態のままなのです。
そして話は、次のページにドンドン展開していくわけです。
またエレキギターを弾き始めようかな?でも楽器を弾くためのパワーが足りない
自分がエレキを弾いている動画を撮ってみた!
まとめ
温故知新(ふるきをたずねてあたらしきをしる)は、孔子が教えた科学へのアプローチの仕方を弟子が「論語」に記したもの。
過去の事象を自ら考え、将来に向けた課題を見直すことには輝かしい未来への期待が託されており、DIYの復興精神と一致する。
私は既に人生の65%を使ってしまったが、残りの35%をその覚醒と復活の時間にしていきたいと思う。
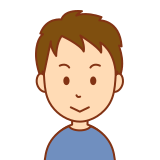
テレビ番組の「人に歴史あり」みたいだったな…。

つまんなかったかな?ごめんごめん。
今後の話の展開に向けて、プロフィールと気持ちの整理をしておきたかったんだよ!

初心者の私には、興味のある「昔ばなし」でしたよ!


