~DIYで中古物件のリフォーム/壁紙の張替え/浴槽周りのコーキング打ち直し/庭の整地やガーデニングを行って新築同様にした~
何年か前に隣の家の一人暮らしの奥さんから、
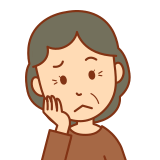
家を売って孫の家のそばに住むことにしました。
昔、もし家を売るときには声を掛けてくれと言われていたので、お宅に伝えます。
という話が舞い込んできました。
私の家を含めた周りの4軒は、同時期に建設された建売住宅。
家の中の老朽度などの度合いは、概ね察しはついており、この辺の中古住宅の相場は知っていました。

これから借金してでも買います。どうしても欲しい。
私はその場でそう返事したのです。
《隣家購入編》

直接売買ではなく、既に仲介の不動産屋さんを通じて手続きを行うことになっていたので、早速、私から不動産屋に連絡。
状況を話したところ、不動産屋もこれまでの話をおばさんから聞いていたそうで、さっさと金額交渉に入りました。
奥さん側からの売買希望額は、少し高かったので、私からは不動産屋に
「この辺の相場は△千△百万円だから、それにマージンの約10%を上乗せしても〇千〇百万円でないと難しいよ。」
と序盤戦の会話が始まりました。
何日かしてから、不動産屋から「あなたの言っていることは、業界の側から診ても正論です。」
「よく査定相場を知ってましたね。」ということで、私の提示した金額で、不動産屋さんが奥さんと息子さんに交渉してくれました。
結果は、ほぼ当方の希望額で合意。
以降、融資してくれる銀行探しが始まりました。
5つの銀行に審査願を出したのですが、前向きな返事があったのは2つの銀行。
結局、家のすぐ近くの銀行が提示した融資金利がビックリするくらいの低金利だったので、そこから融資を受けることにしました。
後から聞いたのですが、私が「今回の物件はどうしても欲しい。」と言っていることや、隣家の奥さんや息子も、知らない人よりも私に売りたがっているという事情が融資決定にかなり影響を与えたのだそうです。
仲介した若い不動産屋さんとは、今でも挨拶程度の連絡を取り合っていて、先日のDMには、「最近、結婚したのだけれど、コロナの影響で新婚旅行は行っていない。」ということが追記されていました。
縁とは不思議な物です。
いつか私の不動産を売ることがあったら、彼にお願いしようと思っています。
さて、話をメインの「家の内装リフォームなどをDIYで行った」という話に入ります。
壁紙リフォームを妻と作業し新築同様
家の明け渡しまでの間には、当然、一通りのリフォームはやってありましたが、妻が「いっその事、隣家と今住んでいる母屋の両方の壁紙を張り替えましょう。」と言って大量の壁紙ロール(糊付き)を通販で仕入れてきたのです。

張替えた室内は新築同様です。
壁紙購入のコツは、糊がたっぷり付いているものを選ぶべし
この壁紙は、専門の壁紙屋さんが通信販売しているもので、
ア 糊がたっぷり塗ってあって、貼り位置の修正がやり易いようになっている
イ 必要な道具(専門の刷毛が各種、カッティングスケール、目地材、カッターなど)がセットになっている
こういうものを選んでいたので、素人のDIYに適したものでした。
早速、妻は各壁の採寸を始めます。
天井から測るので、当然、私がアシスト。
壁紙を無駄にしないよう、小さいところは組み合わせて切り方の工夫を行いました。

下地処理が仕上がり具合を左右する
さて、貼り付け工程ですが、何事も下地が仕上がりを左右するものです。
もともと貼ってあった壁紙を剥がし始めます。
新しい壁紙の定着を考え、ベニヤ板が丸見えになるほどまでは剥がさない方が、下地の隆起が目立たず、また新しい壁紙の糊の定着がよろしいです。
この剥がし作業が全体工程の中で最も時間がかかりました。
なにせ、2階建ての1階部分の壁をほとんど張替えするという施工計画なので、今振り返ってもよくあの短時間でやったなぁと思います。

貼るときは刷毛を使って一気に
購入した壁紙は、糊がベチャベチャに付いているので、大きな壁でも一旦貼ってからベストな位置に動かせます。予定通りです。
位置が決まったら、横幅の広がった刷毛でしごくように空気を抜きながら、壁に定着させていきます。とてもやり易いです。
少し落ち着かせてから、隅を専用のカッティングスケールをあてて、よく切れるカッターでサーッとカットしていきます。
土日の朝から晩まで頑張って予定の範囲を張り替えることができました。

工程中、下地の轍が表面に浮き出している箇所があったので、私が勝手に部分カットして壁紙を再度剥がし、砥の粉で目止めしてから電動のマルチサンダーで下地表面の平滑処理をしたのですが、これが妻の怒りをかいました。
思いのほか平滑化できなかったことに加え、悶々と砂埃をたてたものですから、「イジくらない方が良かったじゃん!」と言われ、何日か無口を貫かれました。(苦笑い)
とにかく、目標どおり、新築同様になったのです。
窓枠の修復
隣家はどういうわけか、室内の各窓枠が変形していたんです。
変形している画像がないのが残念ですが、この窓枠は紙材を圧縮してできていて、表面は木目調のシール貼りなのです。
かっちかちなので、作業している途中まで木材だと思い込んでました。
もともと、紙は木材繊維ですから関連性はあるわけですけど、窓枠の製造加工が容易だったんでしょうね。
窓枠が変形している場所は、2階の1つの部屋と風呂場の横の洗面所、居間であることからすると、ストーブのヤカンなどから強い水蒸気を出していたのでしょう。
木目シールを剥がしてみると、紙材が一旦水分を含んで大きく変形し、そのまま乾燥しているので固く締まっていて圧力を加えての修復は困難です。
このため、カッターで複数切れ目を入れてほぐし、ある程度の形にしてから、エポキシパテを塗り込んで固め直しました。
表面の木目シールは100円ショップにあったものが、たまたま柄が合いそうだったのでそれを使いました。

綺麗に補修できました。
画像を見る限り、上々の仕上がりだと思います。
言わなければわからないでしょ?
しかし、手間のかかる作業の上に、補修が必要な部屋が複数あったので、各所に繰り返し行うのは結構大変でした。
外回りの土木工事をDIY
隣家の外回り工事とは、一体何をやったのか?
ということですが、これが最も過酷な作業だったのです。

画像の左上の方から残土を掻寄せて整地
前のオーナーが、小庭にスチール棚を設置していたのですが、塀の高さと棚の面を合わせたかったのでしょう、地面を2m四方で50cmも深く掘り下げ、地中にブロックなどを敷き詰めていたのです。
これにはビックリしました。
私としては、最初はスチール棚の撤去だけの予定でしたが、その場所にショベルを入れると地中で何かに当たる。
グランドも下がっている。
何だろうと、掘っていくと、ブロックやコンクリート廃材が出るわ出るわ。
掘り下げた分の残土をその他の場所に盛土していたらしく、縁の下の通風口ぎりぎりまでグランド面が上がっていました。

修復の整地作業では、妻の実家から借りてきた金属熊手が大活躍でした。
向こうの方から掻き寄せては地固めを繰り返し、庭全体が平坦になるまで、炎天下の中、丸1日かかりました。


それから、地中のブロックとともに大量のコンクリート廃材や煉瓦が出てきたので、邪魔にならない風呂場の裏口に長穴を掘って全部投入して地固め、その上に踏み石を並べて廃材は路盤代わりにしました。
煉瓦はスロープに再利用しました。
浴槽周りのコーキング張り替え
浴槽周りは、しっかり防水施工しておかないと、日本建築の在来工法では基礎までの袋状になっていて、例えばシロアリ駆除の際にもチェックすることができない構造になっているのです。
思い切って外壁をカットしてやろうとすれば不可能ではないですが、そこまで依頼する人は居ないでしょうね。
チェックできない箇所は、シロアリがやりたい放題してるかもしれないし、そうでないかもしれないブラックボックスなのです。
このため、浴槽下に水が入らないように自己防衛するしかないわけです。
しかし、浴槽周りのコーキングに気を付けている人は意外と少ないようです。

コーキングの張替えは、やろうと思えばそんなに難しくはありません。
まずは剥がし作業、カッターで密着部分に刃を入れながら引っ張っていけばOKですが、新しいコーキングの密着に影響しないよう、しっかり取り除きます。
浴槽タイルとの隙間が大きい箇所には、バックアップ材を押し込んで嵩上げしておくことを忘れないようにしないと、コーキングが凹んで水が溜まり、汚れやカビを誘発することにもなります。
さて、丁寧にやらなければならない下処理の中心となるのがマスキング。
マスキングがしっかりしていれば、綺麗に仕上げることができます。
これが終われば、コーキングをコーキングガンに装着して、息を止めて一気にコーキング材を充填していきます。
塗り替えしは厳禁です。
一方向にガーッと充填していきます。
一周終わったらヘラでマスキングテープの上まで一気に均していきます。
最後に、コーキングが半渇きになった時にマスキングテープを取り除きます。
この時に一方向で剥がさないとコーキングのツヤツヤの面にテープが触れて形が崩れてしまうので十分注意してください。

コーキング材は、硬化が早いものだと扱いにくいです。
おすすめは、変成シリコンのPOSシールかシリコーンシーラント。

その他の物しかなければ、最低でも防カビ材配合の変成シリコン剤が必要です。
とても大事な施工となりますので、仕上がりイメージや自信がない方は、プロに任せた方がベターですね。
【まとめ】

壁紙やコーキングは私にも出来そうだわ!

壁紙選びは絵柄以外に、付いてる糊の量が大事なんだよ。
壁紙購入のコツは、糊がたっぷり付いているものを選ぶこと。
古い壁紙は、ベニヤ板が丸見えになるほど剥がさない方が、下地の隆起が目立たず、新しい壁紙の定着がよい。
自分で外回りの土木工事。
浴槽周りは、日本建築の在来工法では基礎までの袋状なため、シロアリ駆除の際チェックできない構造。浴槽コーキングが重要。


